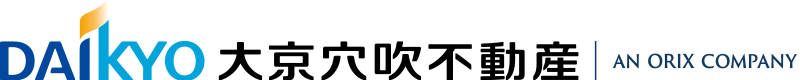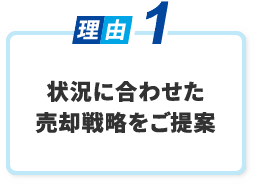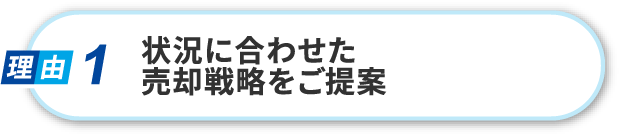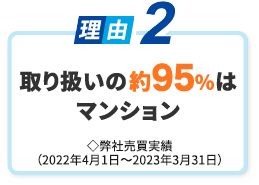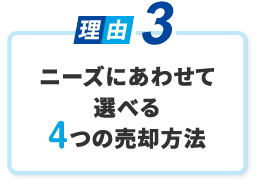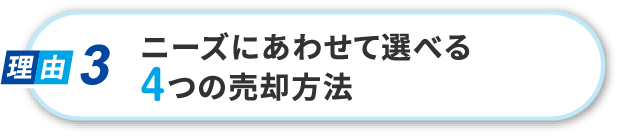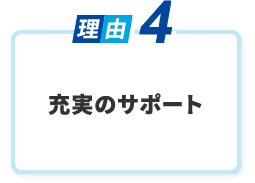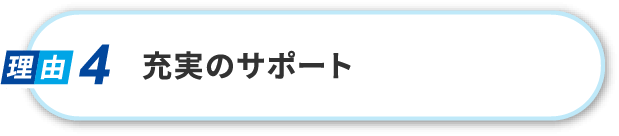2025年の経済と不動産マーケット予測 -家選びのリスクとチャンスとは?-

目次
今回は、直近(2025年1月)の景気、不動産マーケットの状況を確認したうえで、社会、経済の大きな変化の下、不動産投資や家選びにおけるリスクやチャンスをどのように見出していくのか、著者の視点で東京都内の都心不動産に焦点をあてて概説いたします。
【1】景気
政府(内閣府)月例経済報告〈2025年1月〉によりますと、「現状については、景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、 緩やかな回復が続くことが期待される。」と公表されています。
日本銀行の経済・物価情勢の展望(2025年1月)においても、2025年の日本経済について、「海外経済が緩やかな成長を続けるもとで、緩和的な金融環境などを背景に、所得から支出への前向きの循環メカニズムが徐々に強まることから、潜在成長率を上回る成長を続けると考えられる」としています。ただし、国際情勢、海外景気の下振れや金融・為替・市場の動向やその経済・物価への影響に注視すべきと留意点を挙げています。
日本銀行が公表した「全国企業短期経済観測調査(短観)の業況判断DI(「良い」-「悪い」・%ポイント)2024年12月発表」、では以下の数値となっておりました。
この数値から読み解ける内容として、この一年間、業況判断が穏やかに上向いてきていると考えられます。
金利の動きについては、2024年3月の日銀金融政策決定会合により異次元緩和から普通の金融政策へ変更する歴史的転換点になりました。短期金利を7月には0.25%、2025年1月24日には0.25%から0.5%へと引き上げ、日銀は今後も利上げを続ける方針を表明しています。金利がさらに上昇すれば、住宅ローンの調達額の減少、不動産価格の下落に繋がる可能性があり、収益物件のキャップレートは上昇すると想定されます。
【2】不動産マーケットの現状
(1)需要と供給
都心不動産ではマンション用地不足とともに、建設資材の高騰、建築人材不足による工期の長期化にもかかわらず、新築マンション供給数は、2025年は前年比13.0%増の2.6万戸。東京23区では大型タワーマンションがけん引し大幅増となると予測されています(不動産経済 マンションデータ・ニュース 株式会社 不動産経済研究所による)。
さらには金利の上昇で、パワーカップルであっても給与所得世帯が買えるマンションの限度額は下がるのではないかと推測されます。一方で2 億円以上の高価格帯マンションには、外国人投資家を中心に強い買い意欲が続くのではないかと推測されます。
(2)価格、賃貸マーケット
マーケットウォッチVol.10で取り上げているように都心エリアのマンション価格は、右肩上がりで上昇しています。これには、在宅勤務の拡大やマンション価格の高騰による賃貸需要の増加、さらには賃金上昇といった要因が賃料上昇を後押ししていることもあり、東京23区における賃貸住宅においても賃料が上昇傾向にあります。(図1:東京23区のマンション賃料より)
【3】今後のマーケットを考えるうえでの社会、経済の構造変化
今後のマーケットを考えるうえで、「少子高齢化、人口減少、AI/ICT進展による人々の生活の変化、ESG・SDGsの進展、外国人の労働者の増加といったグローバル化」など昨今日本で起きている社会の大きな構造変化は、不動産マーケットに大きな影響を与える可能性がある課題でもあるといえます。ここではその課題から見えた不動産の動向について紐解いていきます。
(1)少子化、高齢化による人口減少、人口移動、空き家問題
日本の人口は2008年をピークに減少し続けており、また国立社会保障・人口問題研究所(令和6年4月12日公表)によると世帯数は2030年をピークにその後減少すると言われています。
したがって不動産投資をする際には、需要が低下すると見込まれる地域か、そうでもない地域かを見極める必要があります。人口は、東京への一極集中の流れが続いており、特に10代、20代の若年層の流入が大きくみられます。
また、高齢化に伴って多様な高齢者向けの不動産需要が顕在化しています。特に高齢単身者の孤独死や認知症などの問題が増加する可能性があり、その対策が急務といえます。
さらには、空き家問題も大きな課題です。空き家は、「令和5年住宅・土地統計調査」によりますと、空き家数は9 0 0 万戸と過去最多となり、また空き家率も1 3 . 8 %と過去最高となりました。
(2)グローバル化、外国人の増加
人口減少とは逆の動きですが、外国人の増加によるマーケットの変化も中長期的には検討事項となる課題です。日本における外国人労働者数は令和6 年1 0月末時点で約2 3 0 万人となっており、過去最多を更新しています。外国人労働者が増加することで言葉の問題、生活習慣の違いといった課題も出てきています。
また、宿泊施設など観光産業においては、インバウンドの動きは重要なポイントです。2 0 2 4 年の訪日外客数は3 6 . 9 百万人と過去最高を記録しました。このペースが維持できれば政府目標( 6 , 0 0 0 万人)に近い水準まで増加する見通しです。
(3)国際情勢、外国人投資家の動き
投資を考えるうえで考慮しておくべきことの一つに、市場の国際連動性があります。
大規模な資金が世界中を駆け巡っており、日本における企業業績とは関係のない動きをするときがあります。特に、海外投資ファンドによる日本株やJ-REITへの投資残高が全体の20-30%になってきている現在、国内投資家もこの事実を無視できなくなってきました。
日本の景気、不動産マーケットは、トランプ政権の誕生など、世界情勢やそれに伴う海外景気の流れ、金融・為替市場の動向に影響を受けやすいといえます。
図2(世界の主要都市のマンション市場の価格・利回り 2024年10月)から、世界的にみて日本の主要都市である東京のマンションは、相対的に不動産価格( 単価)が低く、投資対象としてのイールドギャップ(投資物件と利回りと借入金の金利の差)が大きいことが読み取れます。したがって、外国人投資家、特に東アジアの投資家にとって、まだまだ魅力的であると考えられます。
(4)コロナ禍などパンデミック以降のオフィス需要の変化
コロナ禍により、「オフィスは何をする場所なのか」という疑問が生じ、高賃料の賃借面積を減らす動きが出てきました。
2024年においては、コロナ禍前と同じ通常の出社に戻す企業がある一方、リモートワークでの勤務を中心とし、出社を減らす企業も一定数存在しています。出社を減らす企業は都心のオフィスを縮小する動きを取ってきました。企業、業種によって対応はさまざまですが、社会全体で見れば出社とリモートワークの二極化が進んでいると考えられ、オフィス需要の変化が起きているといえます。2 0 2 5 年もこの動きは変わらないと推測されます。
【4】不動産投資におけるさまざまなリスク要素
個別の不動産投資、不動産保有において検討すべきリスク要素について、簡単におさらいしておきましょう。
(1)大規模災害に対する所有者としてのリスク
地震、大雨、洪水、土砂崩れなどの自然災害の増加に対しての備え、特に老朽化した貸家には、所有者リスクがあり、耐震補強など適切な対応をしていないと、大災害時に無過失の所有者責任を問われ、損害賠償を請求される可能性があります。水災に対しては、2024年10月より、火災保険料率が地域のリスクに応じて5区分に細分化された保険料率によって、地域ごとに保険料が異なるようになりました。
いずれにしても、これから投資する場合は災害リスクを考慮した立地が重要であり、ハザードマップを調べ、土地の地盤リスク、建物の耐震性リスクのほか避難訓練の実施なども含めたBCP対策が機能しているかを見極める必要があります。
(2)法規制強化のリスク
法規制の動きにも注意が必要です。2025年4月から東京都では、新築住宅などへの太陽光発電設備の設置、断熱・省エネ性能の確保などを義務付ける制度が始まります。イギリスやEUにおいては、EPC(Energy Performance Certificate:建物エネルギー性能証明)に適合する環境性能を備えていない貸家は既に賃貸禁止になっており、投資対象としては大きく見劣りする「座礁資産」になっています。日本でも将来イギリスやEUと同様の規制が導入される可能性があるかもしれません。
(3)管理運営リスク
適切なプロパティマネジメント(適切なメンテナンス、大規模修繕、テナントリーシング)がなされないことによる、コスト増、耐用年数の短期化、それに伴う価値の低下のリスクがあります。マンションにおける大規模修繕の履歴や今後の予定、修繕積立金額が十分かどうかなどを投資前に精査する必要があるといえます。
(4)市場リスク
不動産の価格、賃料、空室率は、需要と供給の関係により決まり、一定のサイクルで動いています。それぞれの地域、アセットの種類によりサイクルがあるため、注意する必要があります。なお市場リスクには、市場変動リスクのほか、流動性リスク、インフレリスク、信用リスクなどがあります。これらのリスクも念頭に置いて見極める必要があるといえます。
【5】まとめ
実需層である給与所得層にとって、都心の新築マンションはすでに手の届かない価格になっていますが、さらに今後の金利の上昇によって、新築に向いていた需要層が中古物件や郊外の戸建て住宅へシフトし、所有から賃借へという流れでマンション賃料も上昇するものと予測されます。しかしながら、人口減少などの大きな社会経済の流れの中で、すべての物件がこのような傾向にあるという訳ではなく、地域によっても傾向が異なるため、それぞれのリスクやチャンスを見極める必要があるといえます。
例えば、災害リスクに関しては、ハザードマップなどを確認しながら、リスクが高いエリアの物件を選ぶ際は、その対策が行われているかどうかを見極めるといった話です。
また、購入者自身がローンを組む場合、今後予想される金利の上昇や万一不動産価格が下落した際にも、返済が可能かなど、今後の動向をしっかり見極める必要があるといえます。価格上昇が継続する局面では、チャンスとなり好転すると考えられますが、中長期的な視点で見た際、例えば金利上昇が続くことがリスクとなる場面もあるかもしれません。
ICT、AIの進展もあり仕事のあり方が変質し、リモートワークが増え、若年層を中心にワークライフバランスを重視する考えが浸透するといった仕事に対する価値観の変化がコロナ禍以降で急速に起きた印象です。
家を選ぶ際には、投資という観点のみで有利かどうかだけではなく、自分のローンの返済能力を踏まえつつ、自分の人生観にあった家選びというのも大事になってくるのではないでしょうか。
Writer
村木 信爾 氏
不動産鑑定士、不動産カウンセラー、FRICS、京都大学法学部卒、ワシントン大学MBA。
信託銀行にて、不動産鑑定、仲介等の業務に携わった後、現在、大和不動産鑑定㈱シニアアドバイザー、明治大学ビジネススクール兼任講師(元特任教授)、PROSIL代表。近著に『不動産プロフェッショナル・サービスの理論と実践』(清文社)2022.6刊、がある。